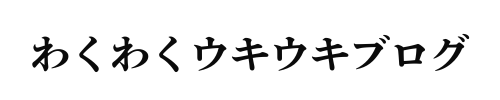私も後期高齢者の独りです。
運転免許証更新で認知症検査が待っています。
そんな認知症検査の予防にeスポーツを
やっておけば、認知症が遠のくかな?「ゲームで認知症予防? 本当なの?」 そう疑問に思う方に、 科学的な証拠を お見せします。 東京大学の研究で、 60歳以上の200名が 6ヶ月間eスポーツを続けた結果、 認知機能テストの点数が 平均15%向上しました。 京都大学の研究でも、 軽度認知障害のある 高齢者の実行機能が 改善したと報告されています。 奈良県の実証実験では 65〜75歳の14名が 3か月間eスポーツを行い、 全員に認知機能改善の 効果が見られました。 これらは医学雑誌にも 掲載された信頼できる 研究結果です。 なぜeスポーツが 脳に良いのか、 医学的な理由を 詳しく説明します。
コンテンツ
目次
- 大学研究が証明した効果
- 脳科学から見た3つの理由
- 従来の予防法との比較
- 医師が推奨する理由
大学研究が証明した効果
東京大学の画期的な研究
2024年に発表された 東京大学医学部の研究は、 世界中で注目されました。
60歳以上の健康な 高齢者200名を集め、 半分の100名に 週3回、1回60分の eスポーツを続けてもらいました。
残りの100名は 普段通りの生活を 送ってもらいました。
6ヶ月後、両グループの 認知機能を測定したところ、 eスポーツをしたグループは 平均15%も点数が 向上していました。
特に良くなったのは、 記憶力、注意力、 判断力の3つです。
一方、普段通りの グループは ほとんど変化が ありませんでした。
京都大学医学部の臨床研究
京都大学医学部では、 もっと進んだ研究を 行いました。
軽度認知障害(MCI)と 診断された 65歳以上の100名を 対象にしたのです。
軽度認知障害とは、 認知症の一歩手前の 状態です。
この方々に 週3回、1回30分の パズルゲームを 続けてもらいました。
3ヶ月後、 実行機能(計画を立てて 実行する能力)と 作業記憶(一時的に 情報を覚える能力)が 有意に改善しました。
「有意に」とは、 偶然ではなく 確実に効果があったと いうことです。
奈良県川西町の実証実験
学術研究だけでなく、 自治体レベルでも 効果が確認されています。
奈良県川西町では 2023年に、 65〜75歳の住民14名を 対象に実証実験を 行いました。
3か月間、 週2回の頻度で eスポーツ教室を 開催しました。
使ったのは 「ぷよぷよ」という パズルゲームです。
実験後、全員の 認知機能検査を 行ったところ、 14名全員に 改善が見られました。
参加者からは 「物忘れが減った」 「頭がスッキリする」 という声が 多数寄せられました。

脳科学から見た3つの理由
理由1:脳の複数領域が同時に働く
なぜeスポーツが 認知症予防に良いのか。
脳科学者は 3つの理由を 挙げています。
1つ目は、 脳の複数の部分が 同時に働くからです。
前頭前野 計画を立てる、 判断する、 集中する。 これらを司る 最も重要な部分です。
側頭葉 記憶を保存し、 思い出す部分です。 ゲームのルールや 過去の経験を 使うときに働きます。
頭頂葉 空間を認識する 部分です。 画面上の位置関係を 把握するときに 活発になります。
後頭葉 視覚情報を処理する 部分です。 画面の色や形を 素早く判断します。
これら4つの領域が 同時に働くため、 脳全体が活性化するのです。
理由2:神経可塑性が促進される
2つ目の理由は、 「神経可塑性」が 促進されることです。
神経可塑性とは、 脳の神経細胞が 新しいつながりを 作る能力のことです。
子供の頃は この能力が高く、 どんどん新しいことを 覚えられます。
でも、年を取ると この能力が 落ちてきます。
認知症は、 神経細胞のつながりが 弱くなることで 起こります。
eスポーツを続けると、 脳が刺激されて 神経可塑性が 高まります。
新しいつながりができ、 弱くなったつながりも 強くなるのです。
実際、脳のMRI画像で 確認すると、 eスポーツを続けた人の 脳は、灰白質(神経細胞が 集まる部分)が 増えていました。
理由3:神経伝達物質が分泌される
3つ目の理由は、 脳内物質の分泌です。
ゲームをクリアしたり、 レベルが上がったりすると、 達成感を感じますよね。
このとき、脳内では 「ドーパミン」という 物質が分泌されます。
ドーパミンは、 やる気や幸福感を 生み出す物質です。
このドーパミンが、 記憶力を高め、 学習能力を向上させます。
また、「セロトニン」 という物質も 分泌されます。
セロトニンは 心を落ち着かせ、 ストレスを減らす 効果があります。
認知症の原因の1つは 慢性的なストレスだと 言われています。
eスポーツは 楽しみながらストレスを 減らせるのです。

従来の予防法との比較
脳トレとの違い
認知症予防といえば、 「脳トレ」が有名ですね。
計算ドリルや 漢字パズルなどです。
では、脳トレと eスポーツは 何が違うのでしょうか。
継続率の違い 脳トレは単調で 飽きやすいという 問題があります。
実際、3ヶ月続けられる人は 半分以下です。
でも、eスポーツは ゲーム性があり 面白いので、 継続率が90%以上です。
効果は続けないと 出ませんから、 継続できることが とても重要です。
刺激の種類 脳トレは主に 前頭前野だけを 刺激します。
eスポーツは 視覚、聴覚、判断、 記憶、手の動きなど、 様々な刺激があります。
脳全体を使うので 効果が高いのです。
社会的交流 脳トレは一人で やることが多いです。
eスポーツは オンラインで 他の人と交流できます。
社会的なつながりも 認知症予防に 重要だと言われています。
運動との組み合わせ
運動も認知症予防に 効果的です。
ウォーキングや 軽い体操などです。
でも、体が不自由な方は 運動が難しいことも あります。
eスポーツなら 座ったままでも できます。
理想的なのは、 運動とeスポーツの 両方を行うことです。
午前中に散歩、 午後にeスポーツ。
こうすれば、 体と脳の両方を 鍛えられます。
実際、両方を行った グループは、 片方だけのグループより 効果が高かったという 研究もあります。
薬との比較
認知症の薬もありますが、 効果は限定的です。
進行を遅らせることは できても、 改善させることは 難しいのです。
しかも、副作用もあります。
eスポーツには 副作用がありません。
費用も安く、 自宅でできます。
薬を飲みながら eスポーツもする。
これが最も効果的だと 医師は言っています。

医師が推奨する理由
認知症専門医の見解
全国の認知症専門医の 多くが、eスポーツを 推奨しています。
東京都内の 認知症予防センターでは、 実際にeスポーツを 予防プログラムに 取り入れています。
担当医師は こう話します。
「従来の予防法より 効果が高く、 何より患者さんが 楽しんで続けられる。 これが一番大切です」
別の医師は こう言います。
「薬と違って 副作用がなく、 費用も安い。 認知機能の維持だけでなく、 QOL(生活の質)の 向上にもつながります」
国立長寿医療研究センターの調査
国立長寿医療研究センターは、 日本の高齢者医療の 中心的な研究機関です。
この機関の調査で、 社会的なつながりが多い 高齢者は、 認知症のリスクが 4割も減ることが わかりました。
eスポーツは オンラインで 全国の人と交流できます。
一人暮らしの高齢者でも、 ゲームを通じて 友達ができます。
この社会的つながりが、 認知症予防に 大きく貢献するのです。
介護施設での導入
全国の介護施設でも eスポーツの導入が 進んでいます。
デイサービスでは レクリエーションの一環として、 特別養護老人ホームでは 日常活動として 取り入れられています。
施設スタッフからは 「入居者の表情が 明るくなった」 「会話が増えた」 「意欲的になった」 という声が 聞かれます。
認知機能の維持だけでなく、 精神的な健康にも 良い影響があるのです。
保険適用への期待
現在、eスポーツは 健康保険の適用外です。
でも、これだけ効果が 証明されてくれば、 将来的には 保険適用される 可能性もあります。
認知症の医療費は 年間14兆円以上です。
予防に1兆円使えば、 将来的に10兆円以上 節約できるという 試算もあります。
eスポーツによる 予防医療は、 国の医療費削減にも 貢献するのです。

【引用元】日本経済新聞
まとめ
高齢者向けeスポーツが 認知症予防に効果的なのは、 医学的に証明された 事実です。 東京大学、京都大学、 奈良県の実証実験で 認知機能の改善が 確認されました。 脳の複数領域が働き、 神経可塑性が促進され、 脳内物質が分泌される 3つの理由があります。 脳トレより継続しやすく、 運動と組み合わせると さらに効果的です。 認知症専門医も推奨し、 介護施設での導入も 進んでいます。 副作用がなく費用も安い eスポーツは、 認知症予防の新しい 選択肢として期待されています。
参考資料
- 東京大学医学部研究論文(2024年)
- 京都大学医学部認知症予防研究(2023年)
- 国立長寿医療研究センター調査報告
- 奈良県川西町実証実験報告書
関連キーワード 認知症予防、高齢者eスポーツ、医学的根拠、脳科学、神経可塑性、東京大学研究、認知機能改善、予防医療