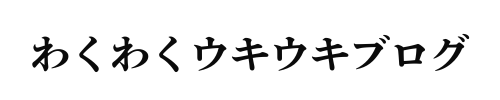子供の頃に手に取った『家の光』という農業雑誌。
そこに描かれていた農家の生活は、
人の手で支えられた温かみのある風景でした。
しかし現代の農業は、機械化やICTの導入により、
かつてとは比べものにならないほど効率化されています。
その一方で、農家の間には新たな「格差」が生まれています。
コンテンツ
『家の光』が語った時代と今の違い
昔の農業|人の力が中心
昭和の頃の農業は、家族総出で田畑を守る光景が一般的でした。農機具は限られており、人の手作業に頼る部分が多かったのです。
現代の農業|機械化と効率化
現在ではトラクターやドローン、ICT技術の導入によって、少人数でも大規模な農地を管理できるようになりました。しかし、この「機械化」は資金力のある農家しか導入できず、格差の要因にもなっています。

【引用元】読売新聞オンライン
農家以外にも広がる格差社会
農業と他産業の共通点
農業だけでなく、社会全体でも「機械化に対応できる人」と「そうでない人」の間で格差が広がっています。教育、就職、医療においても同じ現象が見られます。
地方と都市の違い
都市部の農家は販路や直売所に恵まれ、収入を安定させやすい一方、地方農家は市場価格に左右される収益構造から抜け出せず、二極化が進んでいます。
農家の人たちはどう解決していこうとしているのか?
協同組合や直売所の強化
農家同士が協力し、JA(農協)や地域直売所を通じて販路を広げる取り組みが進んでいます。地域全体でブランド化を進め、消費者に「地元の味」として届ける工夫も始まっています。
スマート農業の導入
補助金や自治体支援を活用し、
ICTやロボット農機を取り入れる農家が増加しています。
これにより高齢者農家でも効率的な農作業が可能になりつつあります。

【引用元】農業機械-クボタ
若手農家の挑戦
若い世代の農家はSNSを活用し、直接消費者に農産物を販売するなど、新しいビジネスモデルを築き始めています。
まとめ|『家の光』の時代から未来へ
昔『家の光』に描かれた農家の姿と比べると、
現代は確かに進歩しました。
しかし、その進歩が新たな格差を生んでいるのも事実です。
農家が未来を切り拓くためには、
協力と革新が欠かせません。
そして消費者である私たちも、
地域の農業を支える選択をしていくことが求められています。
【引用元】表紙農業協同組合新聞より