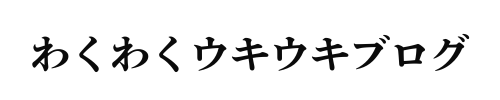令和の時代になり、「化粧をしない中高年」
が増えています。これまでは女性にとって
化粧は社会的なマナーとされてきました。
しかし近年はその考え方が変わり、自然体
で過ごす人が増えているのです。背景には
健康やお金、時間の問題、そして社会や
価値観の変化があります。本記事では、
化粧をしない中高年が増える理由を整理し、
今後の社会やビジネスへの影響も考えます。
コンテンツ
化粧をしない中高年が増える理由1:自然体志向の広がり
令和では「ありのままの自分を大切にする」
価値観が広がっています。SNSやテレビでは
ナチュラルな美しさを肯定する発信が増え、
中高年も「無理に隠す必要はない」と考える
ようになりました。シワや白髪は人生の証で
あり、自然体でいることに価値を見出す人が
増えています。こうした意識の変化は、化粧
をしない選択を後押ししているのです。
化粧をしない中高年が増える理由2:健康と肌のため
長年の化粧習慣で肌トラブルを経験する人は
少なくありません。化粧品に含まれる化学成分
でかぶれたり、肌が弱くなったりする場合も
あります。中高年は健康への意識が高まり、
「肌を休ませるために化粧をやめる」という
考え方が広がっています。皮膚科医も過度な
化粧は肌に負担をかけると指摘しており、
ノーメイクで過ごす人が増えています。
化粧をしない中高年が増える理由3:経済的な負担
化粧品は長期的にみると大きな出費になります。
基礎化粧品、ファンデーション、口紅などを
そろえると毎月数千円から数万円必要です。
年金生活や収入減少に直面する中高年にとって
節約は大切な課題です。そのため「必要最低限」
に抑える人や「完全にやめる」人もいます。
経済的な理由は、化粧をしない流れを広げる
大きな要因の一つとなっています。
化粧をしない中高年が増える理由4:社会の変化
昔は「女性は化粧をして出勤するのが常識」と
されてきました。しかし最近は職場の多様性が
重視され、化粧を強制する空気が弱まっています。
厚生労働省も外見に関する不当な規定は差別に
あたる可能性があると示しています。社会全体で
「化粧をするかしないかは自由」という考え方が
広がっているのです。
化粧をしない中高年が増える理由5:コロナ禍の影響
新型コロナウイルスの流行によりマスク生活が
続いたことで、化粧をしない習慣が広がりました。
「どうせ顔が隠れるから」という理由で化粧を
やめ、そのまま習慣化した人も多いのです。
マスク生活は中高年にとって大きなきっかけと
なりました。
化粧をしない中高年が増える理由6:ジェンダー平等の意識
令和は多様性の時代です。「女性だけが化粧を
強いられるのは不公平」という声が強まり、
男女ともに素顔で過ごす人が増えています。
男性も肌ケアはするけれど化粧はしないという
選択をする人が増えており、性別に縛られない
新しい価値観が広がっています。
化粧をしない中高年が増える理由7:時間の節約
化粧には毎朝多くの時間が必要です。中高年に
なると「その時間を趣味や運動に使いたい」と
考える人が増えます。家族との時間や自分の
学びに使えることも、ノーメイクを選ぶ理由と
なっています。時間の自由は大きな魅力です。
化粧をしない中高年が増える理由8:環境への配慮
近年は環境問題への関心が高まっています。
化粧品の容器や廃棄物が環境に負担をかける
ことが指摘され、環境にやさしい暮らしを選ぶ
人は化粧を控えるようになりました。
「エシカル消費」と呼ばれる考え方が中高年にも
浸透してきています。
化粧をしない中高年が増える理由9:家族や周囲の理解
家族や友人から「化粧しなくてもいいよ」と
言われることで安心する人もいます。社会の
空気が変わったことで、素顔でも人と会える
安心感が広がっています。周囲の理解は大きな
後押しとなっています。
化粧をしない中高年が増える理由10:内面の充実を重視
中高年は外見よりも健康や心の豊かさを重視
する傾向があります。運動や食事、趣味を大切に
することで心身を整え、「外見を作るより内面を
磨く」方向へ価値観が移っています。これは令和
時代の生き方を象徴しています。
まとめ
令和時代に「化粧をしない中高年」が増えている
のは、社会や価値観の変化が大きな理由です。
自然体を尊重する意識、健康や経済的な事情、
環境やジェンダーの問題まで、背景は多岐に
わたります。今後は「化粧をしないこと」も
尊重される選択肢として定着しそうです。
中高年が自分らしく生きる社会は、より豊かな
未来につながっていくでしょう。
【引用元】📖 参考資料:厚生労働省「就業規則に関する均等法の解説」
(https://www.mhlw.go.jp/)
【引用元】表題 LIPS